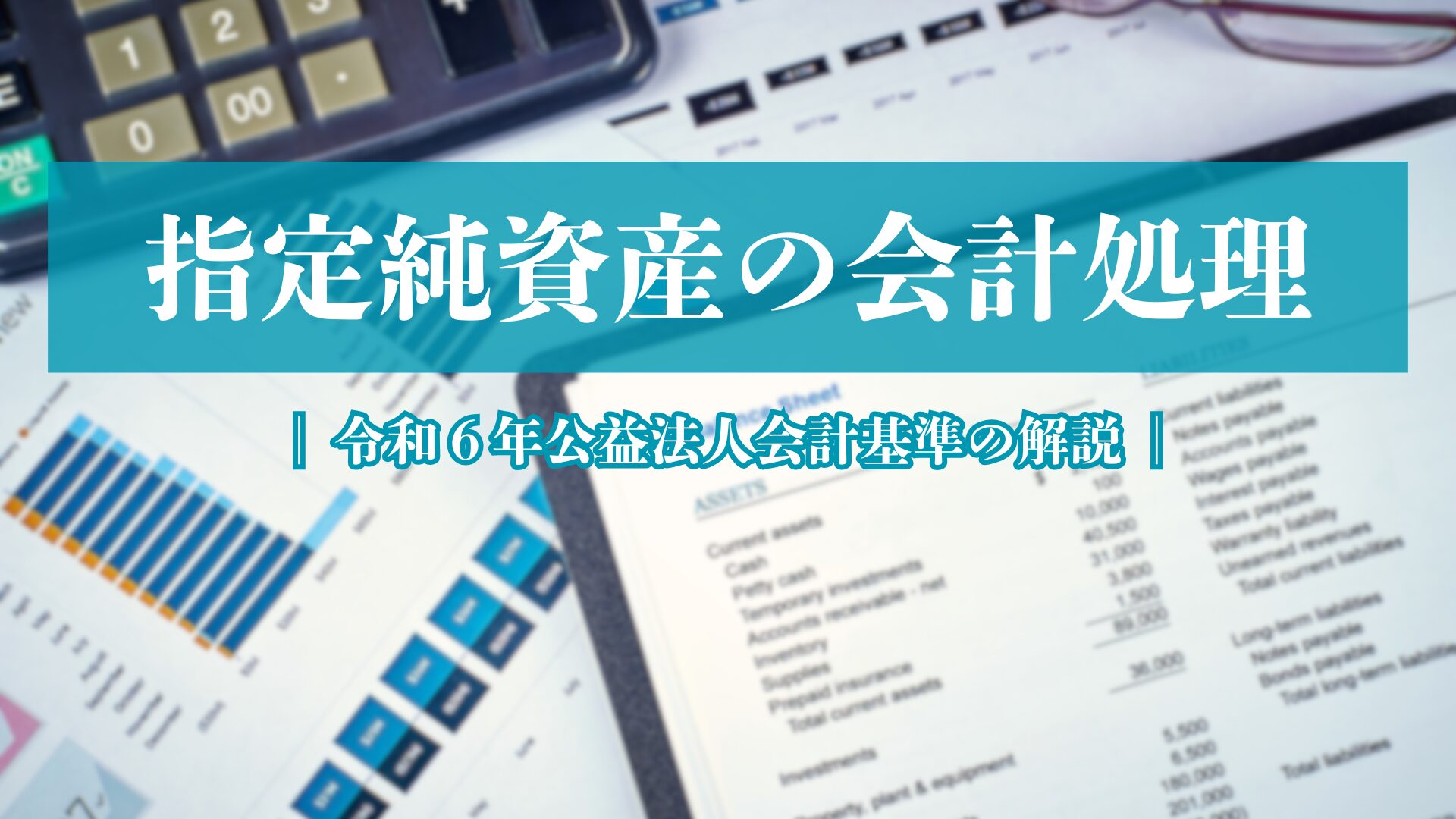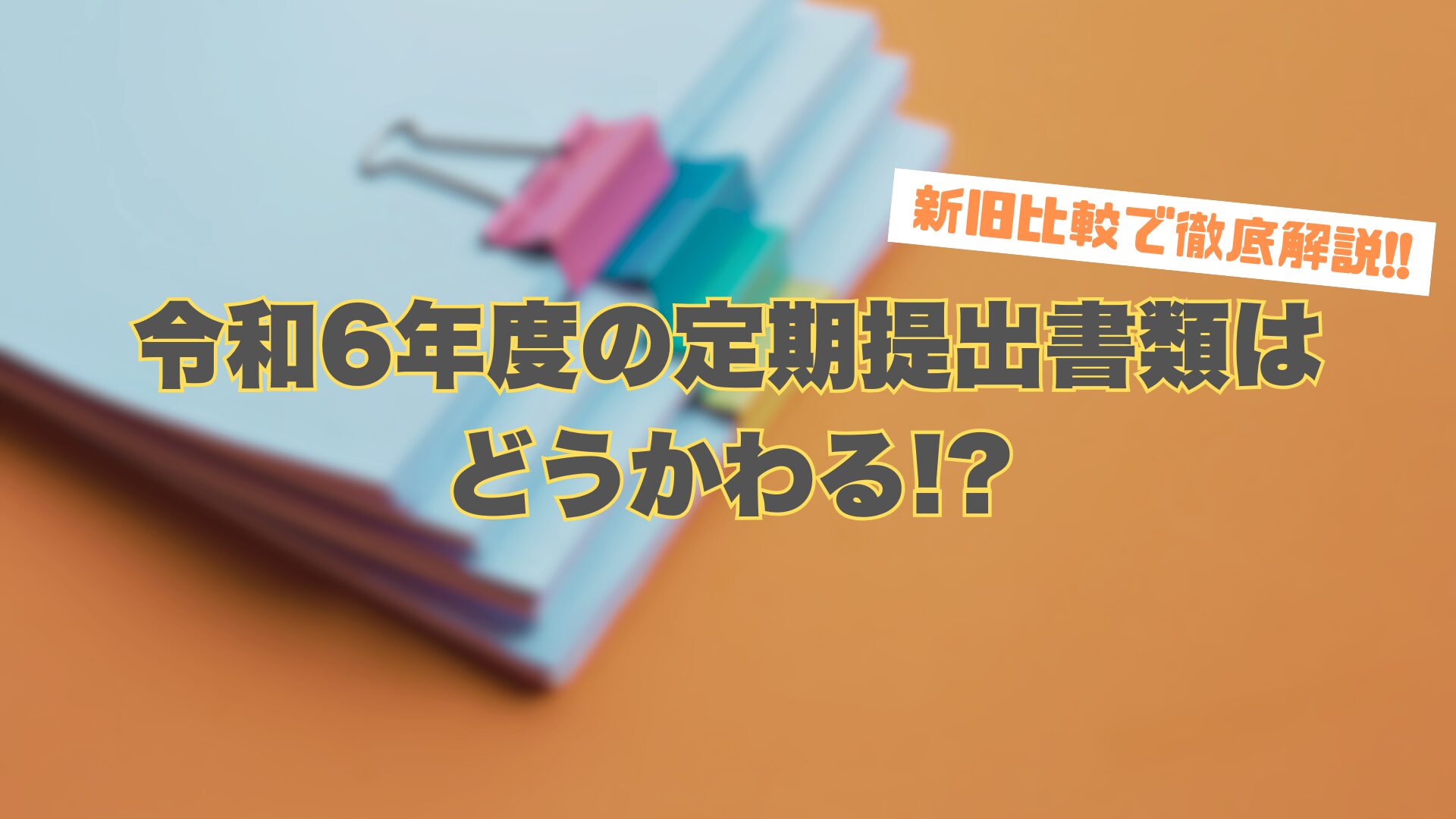【公益法人・相続対策】奨学金財団のすすめ – 社会貢献と相続税対策 –
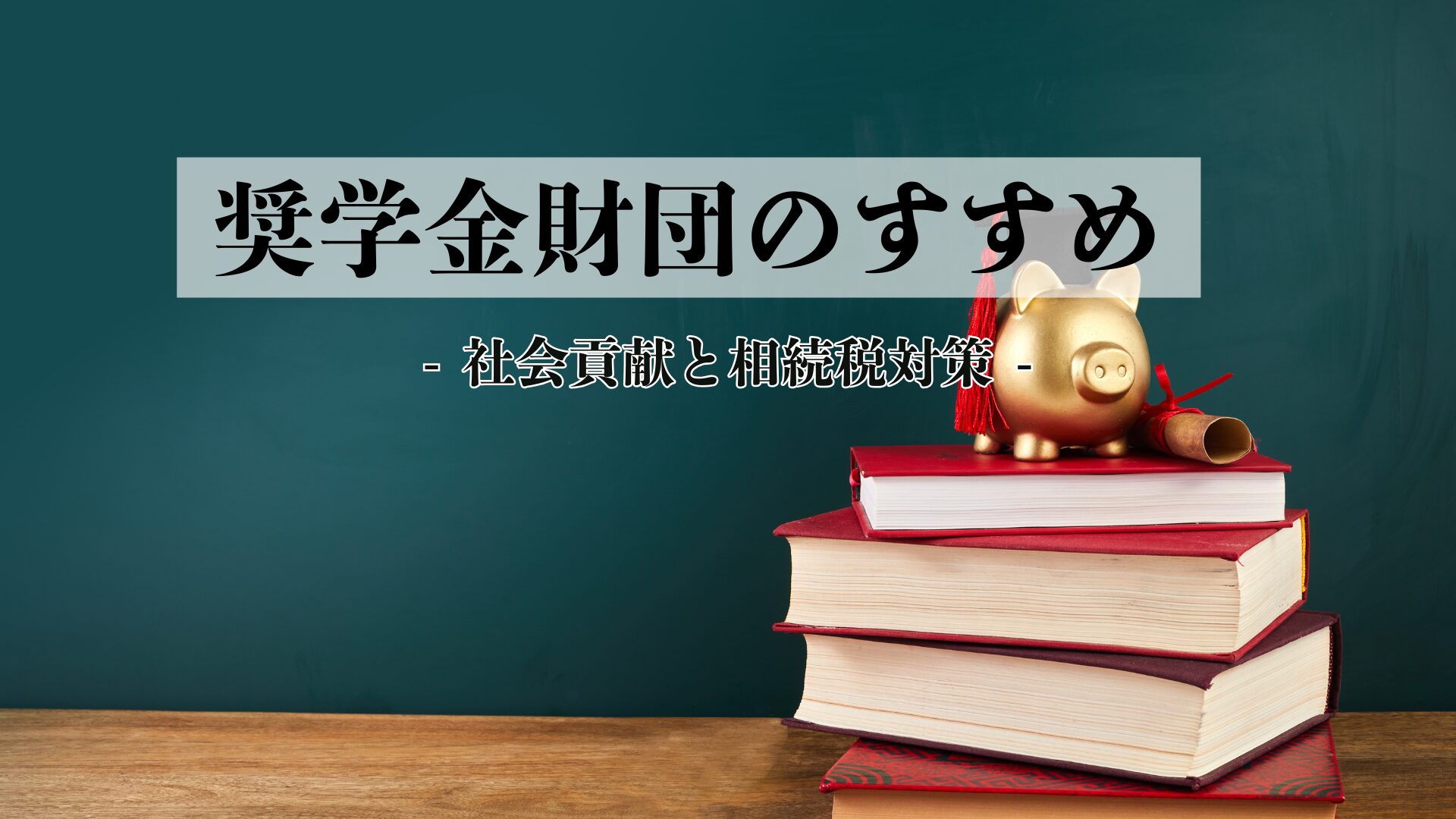
奨学金とは、経済的な理由で学びを諦める若者に希望を与える制度です。
特に返済不要の「給付型奨学金」は、学生の大きな支えとして将来を後押しし、未来ある若者への投資として社会全体の人材育成のために必要不可欠な制度です。
「学びたい気持ちはあるのに、家計が理由で進学を諦める」――そんな若者に手を差し伸べることができるのが奨学金財団の役割です。
いまや奨学金財団そのものは珍しくはありませんが、設立や運営の方法などはあまり知られていないのが実情です。実は奨学金財団を活用することで相続税対策としてのメリットもあるのです。ある程度の資産家の方であれば、相続対策として自分で奨学金財団を設立して運営することが可能です。
今回は奨学金財団を設立しようとしている方にむけて、全体の流れや税務上の取り扱い、弊所でお手伝いできることや費用感などを中心に解説します。
目次
全体的な流れ
まず奨学金財団のセットアップまでの全体的な大まかな流れについて、おさえておきます。
今回は、個人で保有する有価証券を財団に現物寄付を行い、それを財源として奨学金事業を行うことを前提にしています。
- 一般財団法人の設立
- 公益認定の取得
- 現物財産の寄付
一般財団法人の設立
一般財団法人の設立自体は、司法書士先生にお願いすればそれほど難しいことではありません。
ただし財団の設立に慣れていないと、原始定款に記載すべき事項や、公益認定に耐えうる定款の記載事項を漏らしてしまう恐れがあるので、財団設立と公益認定に詳しい司法書士先生にお願いすることをおすすめします。
財団設立に関しては、こちらの記事(【財団法人】設立理由から手続き・期間・費用まで徹底解説!!)でも詳しく解説しているので、良かったら参考にしてみてください。
奨学金財団の設立にあたり最も重要なことは、奨学金事業の内容の検討です。
ここは設立者の意向が最大限反映されますので、じっくりと考えていただきたいところです。
具体的な検討事項は、以下の通りです。
- どのような学生を応援したいのか
- 選考基準をどのように定め、選考委員会の人選をどうするか
- 貸与型か給付型か
- 毎月の給付額はいくらにするのか
といった具合です。
選考委員会の人選は、全体のスケジュール感に影響を及ぼす可能性があるので、早めに検討すべきかと思われます。
選考委員会は財団と利害関係のない第三者から構成される諮問機関であり、選考基準に基づき奨学金候補者の選定を行い、理事会に推薦する機能を持ちます。この仕組みがあるからこそ、奨学金事業としての公益性が担保されます。
この選考委員会の構成員は、教育機関に携わっていた有識者が望ましいです。奨学金財団の設立意向がある方であればそれなりの人脈がおありかもしれませんが、引き受けてくれる人を探すのに時間がかかることも想定されますので、早めに動くべきでしょう。
次に重要なのは、実際の奨学金の金額や対象者にかかわるところです。
これは予算の兼ね合いにもよるのですが、奨学金事業の規模感や対象エリアによっては後述する措置法40条というみなし譲渡の非課税制度の適用要件にかかわってくるところですので、この要件を見据えた金額設定等が必要です。
公益認定の取得
無事に一般財団法人を設立し、事業の骨格ができましたら、次に目指すべきは公益認定の取得です。
あしなが育英会が一般財団法人であるように、奨学金事業を行う上で、公益認定を取得することはマストではありませんが、公益法人に対する寄付は、寄付者に対する税制優遇のメリットがあります。事業の公益性を国から担保してもらうことで、応募者が増える側面もあるでしょう。
奨学金事業で公益認定をとることは、事業の仕組みづくりさえ出来ればそこまでハードルの高いものではなく、後述する措置法40条による税金の優遇措置の適用にあたっては、公益認定をとっておくことで使いやすくなります。
公益認定をとることのデメリットとしては、公益法人としての管理運営が必要となり、一般財団法人と比較すると事務手間がかかるということはあります。その分管理コストもかかります。
ですが後述する措置法40条は、適用して終わりの制度ではなく、適用後もきちんと要件を充足していないと承認が取り消されるリスクが潜んでいます。承認が取り消されれば、譲渡所得が課税されることになります。
公益認定をとっておくことは、財団としてのガバナンスを向上させることになり、措置法40条の承認取消リスクを低減させることにもつながるため、公益認定の取得をおすすめします。
公益認定の取得までスケジュールとしては、奨学金事業の実績作りとして一度決算をむかえてから申請手続きをするのが望ましく、書類の差し戻し等がなければ公益認定申請から4ヵ月程で認定取得が可能です。
決算の有無は申請に関係はありませんので、決算を経ずとも申請すること自体は可能ですが、事業計画や予算書などキッチリとしたものができていることが必要になります。
現物財産の寄付
公益認定が取得できましたら、次に奨学金事業の財源として必要不可欠な有価証券の現物財産を寄付します。
この株式や公社債などの有価証券の運用益を奨学金事業の財源に充てることになります。
現物財産の寄付で避けて通れないのが、所得税法59条のみなし譲渡です。
これは法人に対して無償で財産の移転をしたことをトリガーに発動し、財産を移転したときの時価で売却があったものとみなして、寄付者に対して譲渡所得が課税されるというものです。実際に売却したわけではないのに税金負担を強いられることから、キャッシュなき納税としてその税負担は相当なものです。
寄付者にとっては、自分の財産を善意の気持ちで寄付をするにもかかわらず、さらに税金まで課税されることになり、心情的に納得のいかない制度ではありますが、現行の法令ではそのような取り扱いになっています。
しかしそれでは現物寄付に二の足を踏んでしまい、民間の公益活動を阻害しかねないことから、一定の要件を満たす現物寄付については、みなし譲渡を課税しないという政策的な目的で設けられた制度が、租税特別措置法40条です(この記事では措置法40条と呼んでいます)。
この措置法40条には、一般特例と承認特例の2種類があり、それぞれ細かい要件があるのですが、両者の大きな違いは、一般特例の場合には、承認申請から承認通知まで2~3年の期間を要するのに対して、承認特例の場合には、現物財産が株式の場合には承認申請から3ヵ月で承認がなされる(みなし承認)仕組みになっており、承認までの期間に大きな違いがあります。
さらに承認特例は、承認特例対象法人にのみ認められるものであり、公益財団法人は含まれますが、一般財団法人は含まれないため、承認特例を目指すのであれば、公益認定の取得がマストになります。
公益法人であれば承認特例を無条件で認めるというものではなく、実際には細かい要件を充足していくことになりますが、特に重要な要件としては、寄付者と財団役員の関係性として、当事者と親族関係が排除されているという点です。
具体的には、寄付者本人が財団の役員であったり、寄付者の親族が財団の役員である場合には、承認特例を使うことができません。
通常は設立者の方は、財団役員を兼ねていることが多く、その方のリーダーシップで奨学金事業をセットアップしていくことになりますが、この承認特例を使うタイミングでは、財団役員を降りてもらう必要があります。
設立者が役員をやめることについては、公益認定申請や措置法40条の適用自体に弊害はないのですが、全体の士気にもかかわることですので団体運営を考慮して総合的に勘案して決めていくことになります。
承認特例が使えることと天秤をかけた際には、役員を辞めることの方が優位性はあると思いますが、個別事情によっては一般特例でいくことも選択肢になります。
この措置法40条は、寄付してから4ヵ月以内に申請が必要であることと、その後の確定申告や必要な添付資料もありますので、適用要件の確認も含め絶対に忘れないように注意が必要です。
清塚樹税理士事務所でお手伝いできること
清塚樹税理士事務所では、奨学金財団の設立から運営まで、ワンストップで対応することができます。
業務スコープ
弊所がお手伝いできる主な業務内容は以下の通りです。一部の業務は提携の行政書士先生に依頼することになります。
- 公益認定を見据えた定款作成
- 措置法40条の適用要件に配慮した事業計画及び予算書の作成
- 公益認定の申請書作成
- 奨学金の募集要項など各種内規の作成
- 現物寄付に関する措置法40条申請と税務申告
- 財団法人の記帳業務及び顧問業務
- 全体のスケジュール管理
スケジュール感
財団の役員構成や選考委員会の人選、事務局体制の整備が整ってさえいれば、最短で1年で公益認定の取得が可能です。その後、措置法40条の承認特例が使えたとして、現物資産の寄付完了まで全体として1年半、長くて2年ぐらいはかかります。一般特例で行く場合やこちらで人選のお手伝いまでする場合にはさらに時間がかかるとお考え下さい。
上記のスケジュールは、お客様の公益認定取得に充てられる時間や人的資源、対応能力、そもそもの熱意がどれだけあるかによって左右されますので、あくまでも参考程度にお考え下さい。
超特急で対応が必要な場合には、別途上乗せ報酬が発生しますが、案件状況に応じて適宜対応しますのでご相談くださいませ。
料金
料金は案件状況において異なりますので、こちらもあくまで目安としてお考えください。
| 業務内容 | 金額 |
|---|---|
| 公益認定の取得までにかかる費用 | 税抜100万円(別途税)~ |
| 公益認定の取得から措置法40条の手続までにかかる費用 | 非課税適用により軽減される税額×1~10%の割合を乗じた金額(割合は案件状況や資産規模に応じて変動) ※最低報酬金額は税抜100万円(別途税) |
| 記帳業務及び顧問業務 | 料金表に基づく(記帳業務が発生する場合には、料金表に記載の金額×2でお考え下さい) |
おわりに
奨学金財団を設立することは、教育機会の拡大とともに、寄付者にとっても大きな意義を持つ取り組みです。社会貢献をしつつ、ご自身の税金対策にも効果があります。
ただし奨学金財団のセットアップにはそれなりの時間とコストがかかります。設立意向のある方がどれだけコミットできるかに左右されるため、節税だけに重きを置きすぎるとうまくいきません。奨学金事業を通じて社会貢献をする!という熱量が非常に重要です。